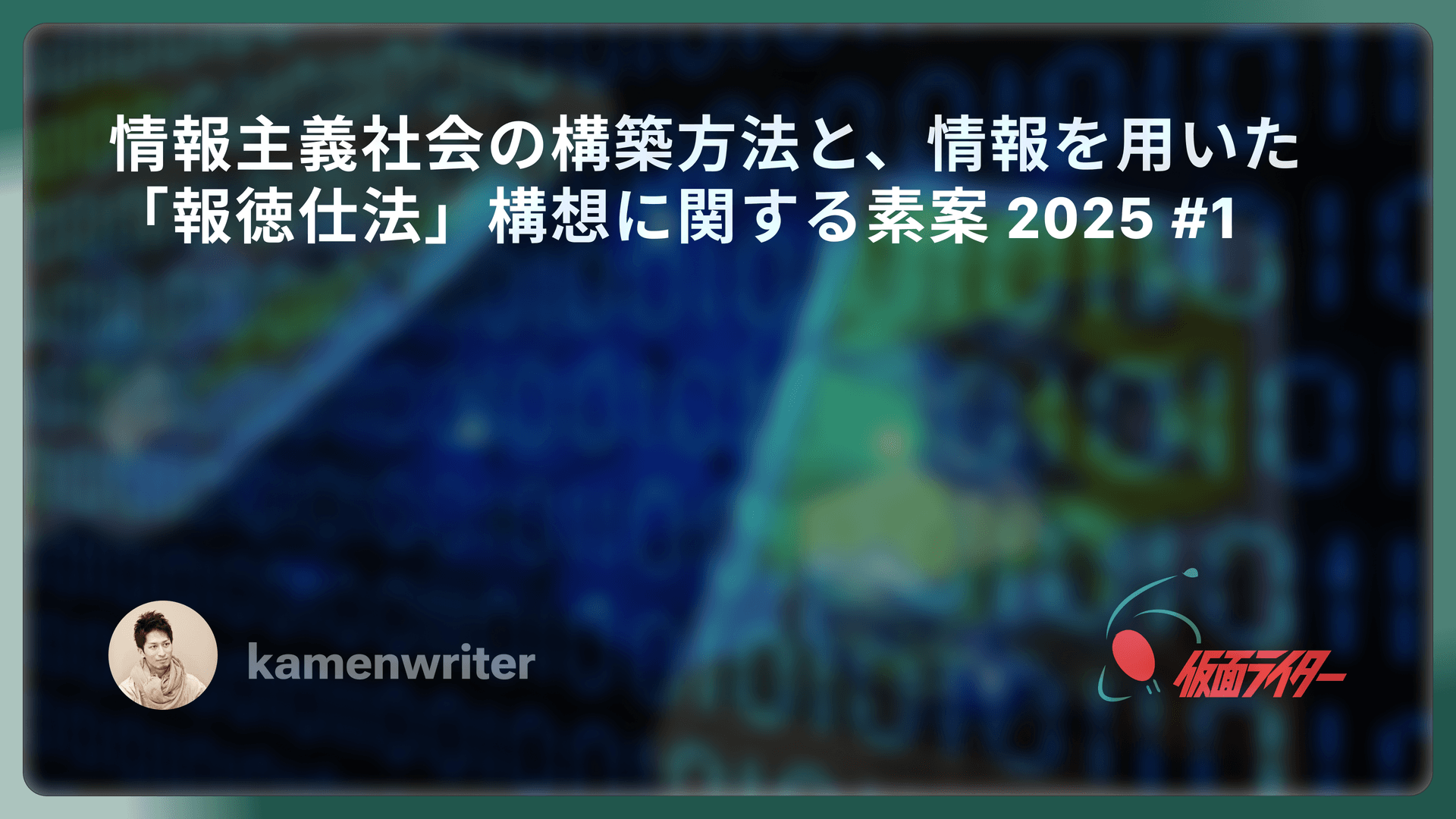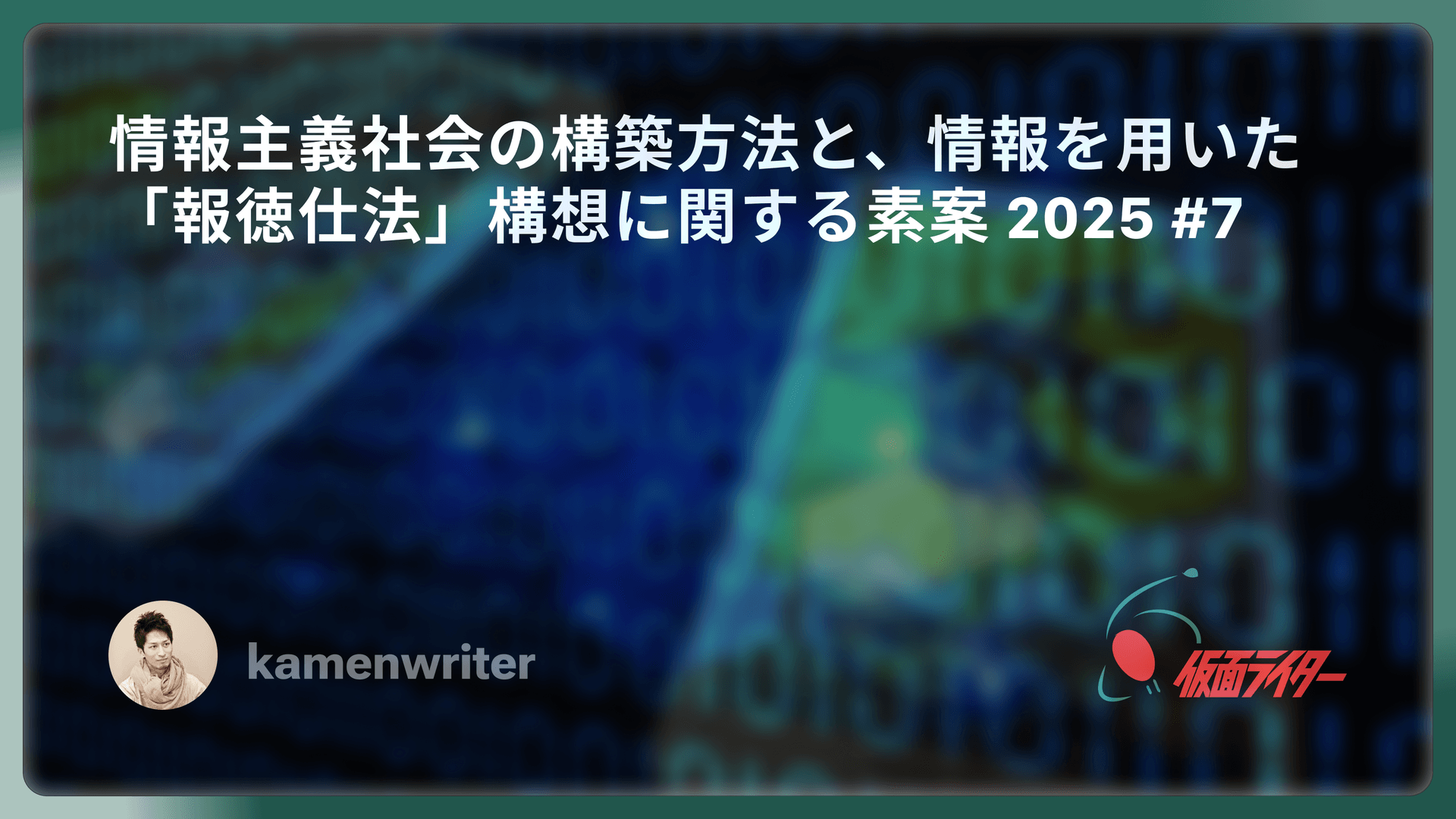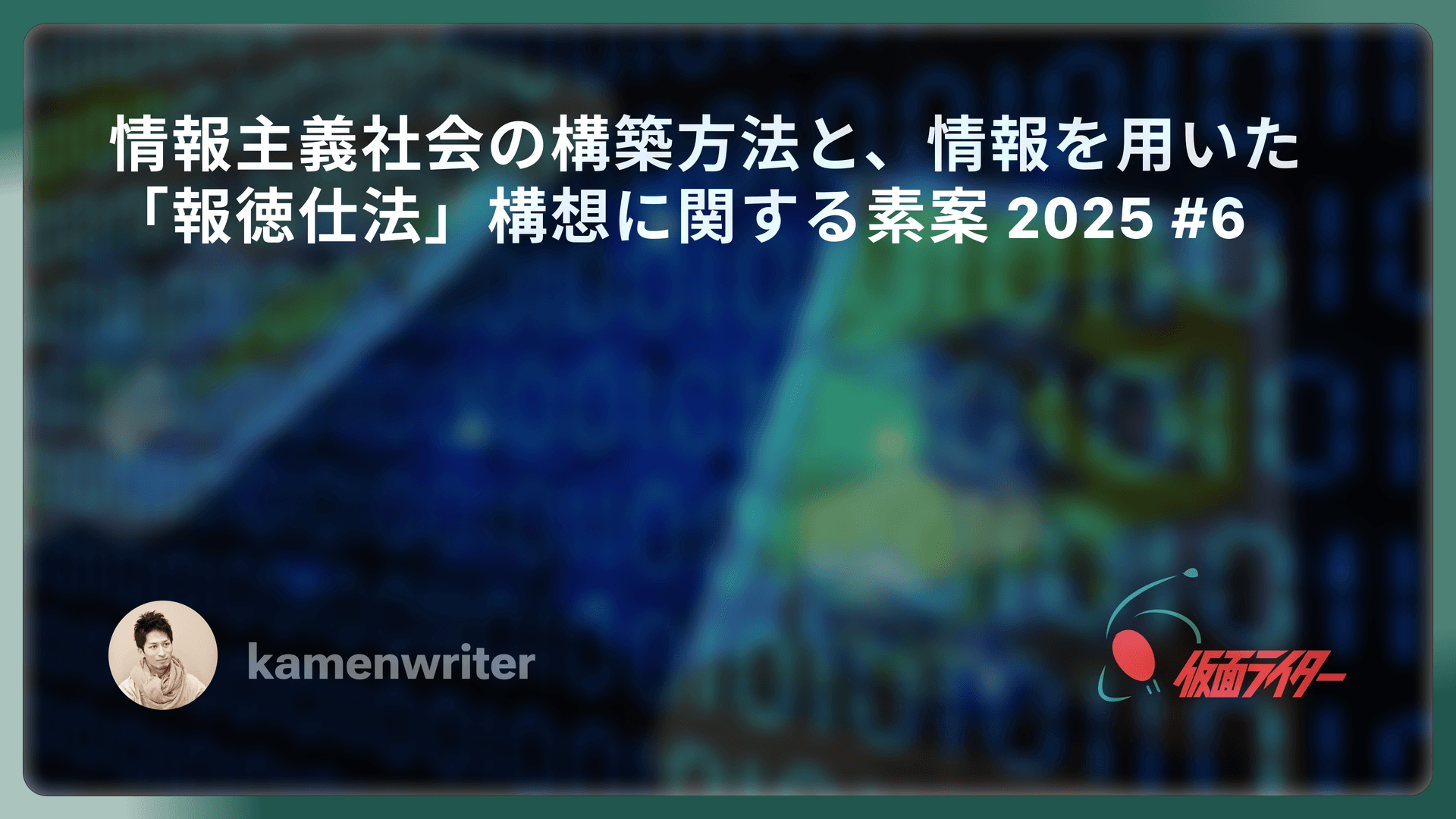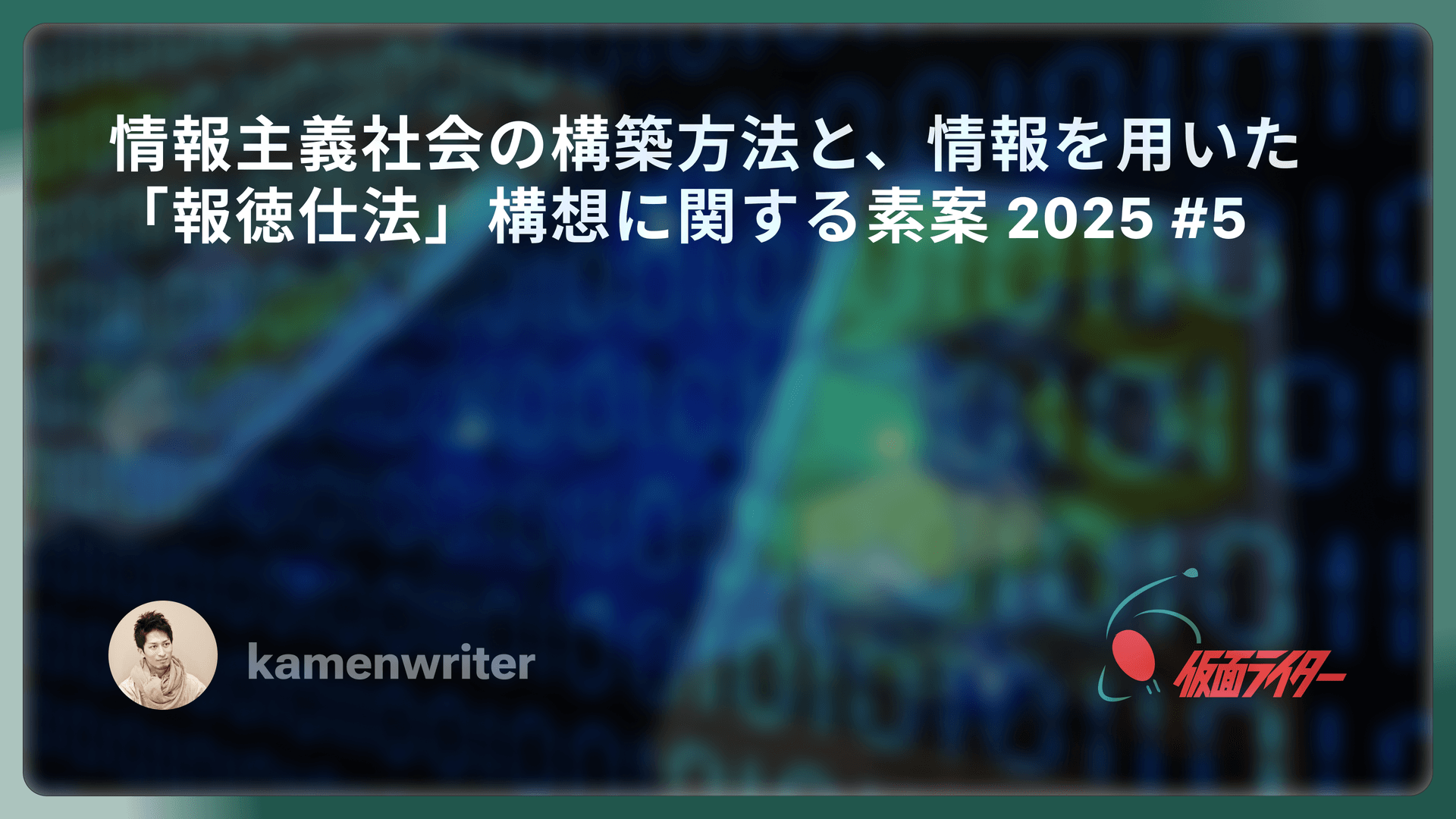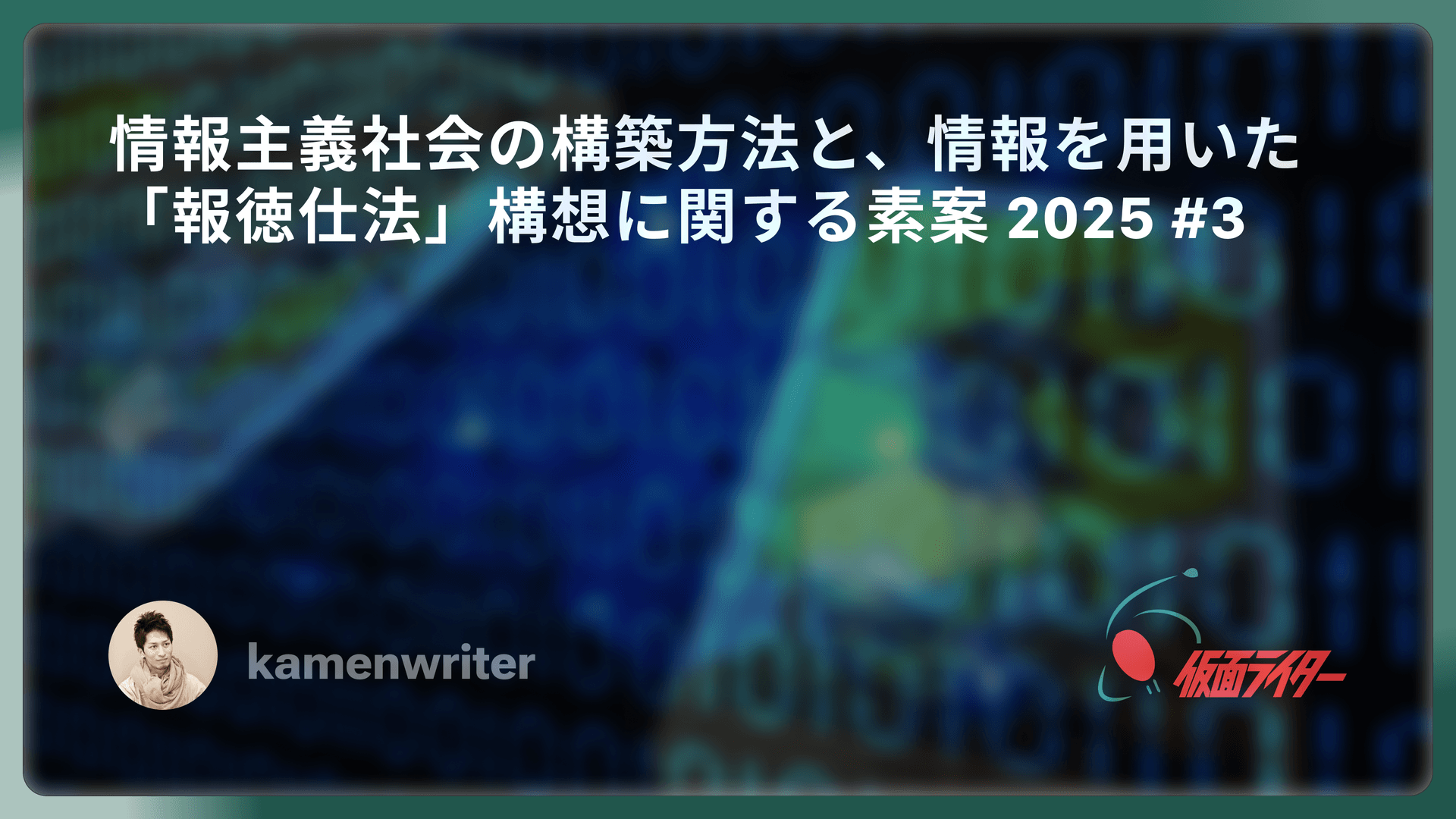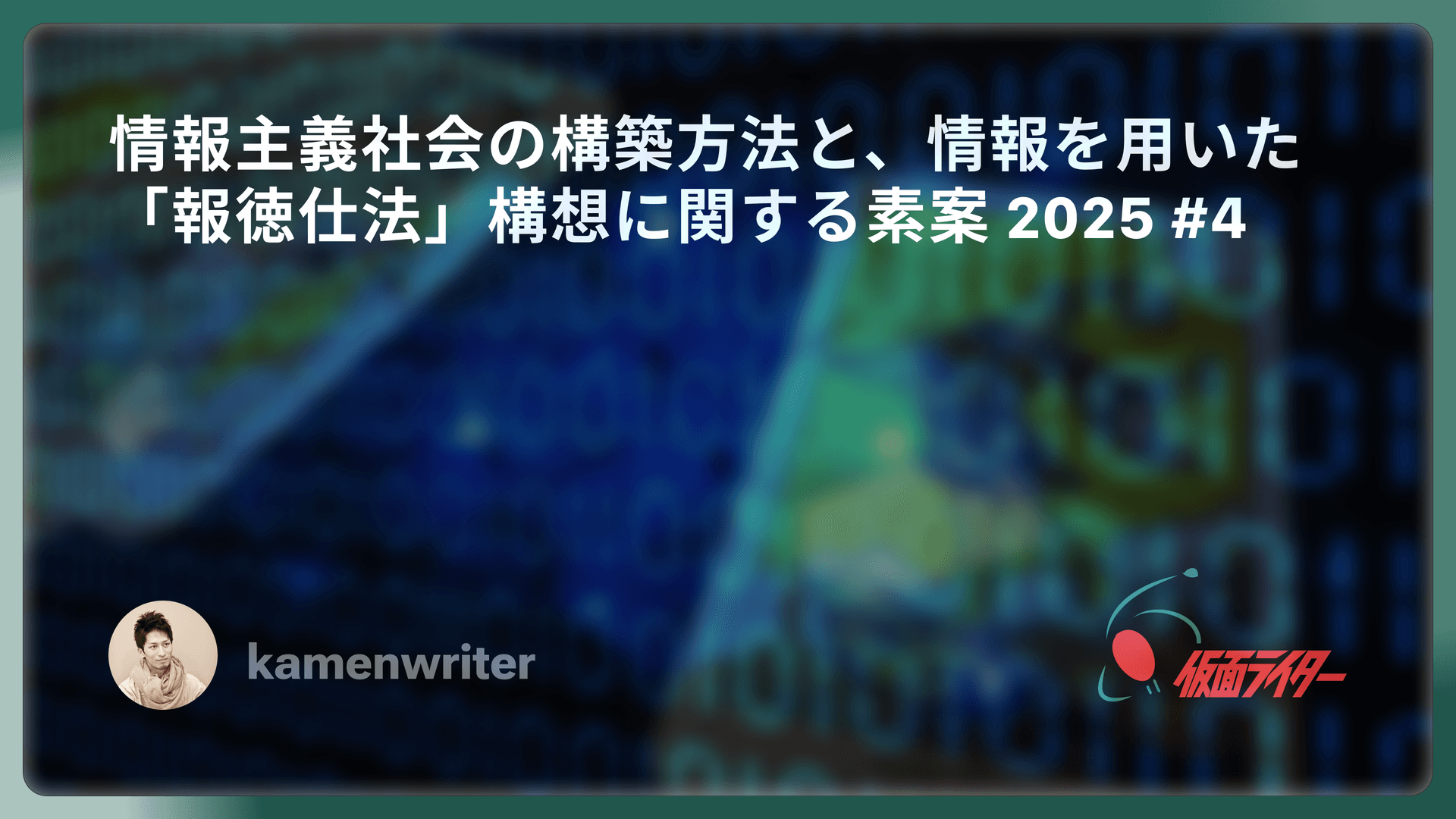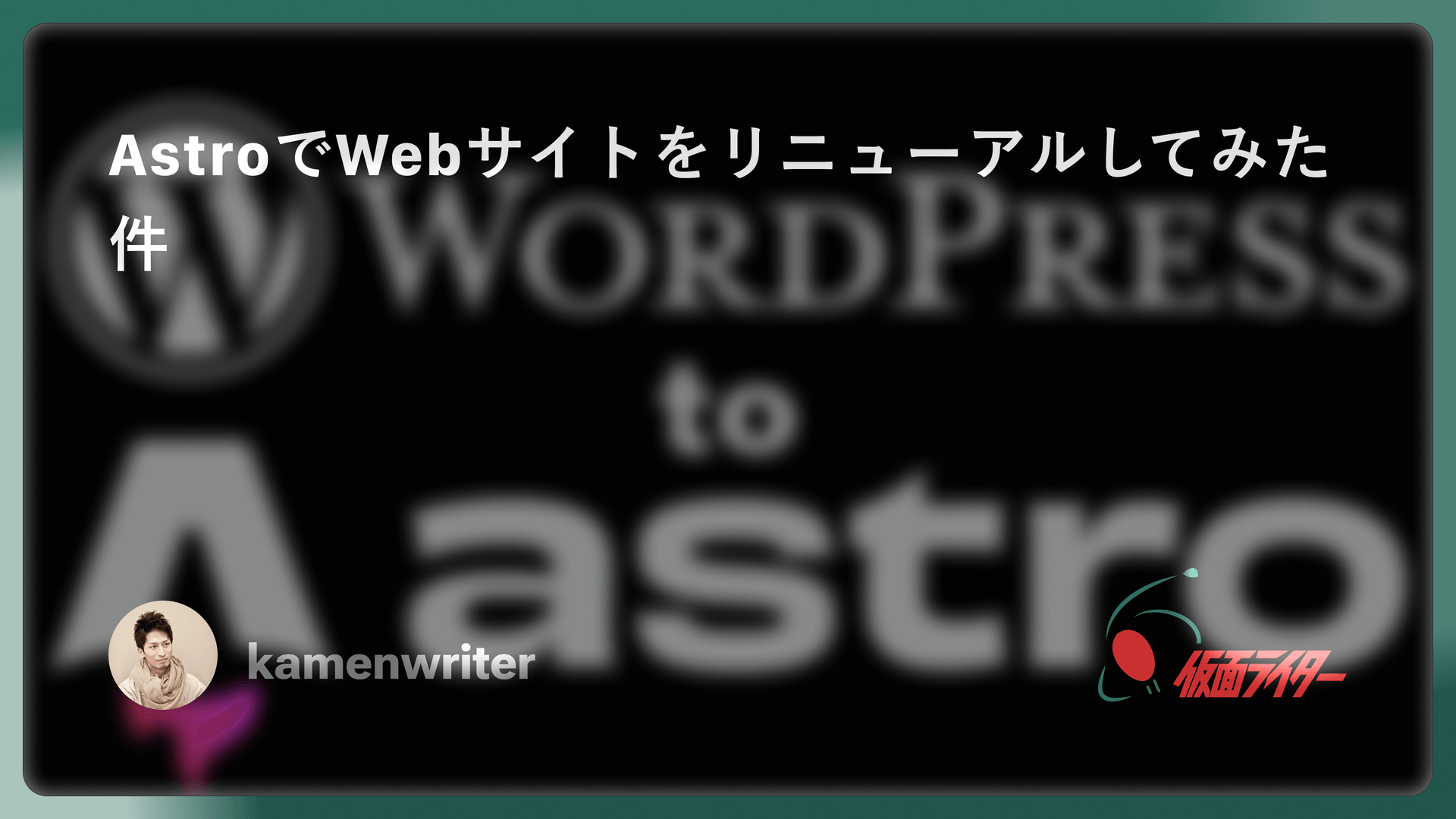序
社会的に何者でもない人物が掲げるには、随分と大仰なタイトルかもしれない。しかしこれは、インターネットという広大な海に漂う、ただの与太話に過ぎない。気楽な埋め草のつもりで、お付き合いいただけると幸いである。
書き手である本人としても、何にもならない余計な論考に時間を費やすより、少しでも実になる仕事や具体的な取り組みに着手すべきだと感じている。それでも、これから取り組むことの背景を整理し、あらかじめ思想を深掘りしておくことが、結果的には遠回りどころか、むしろ近道になるのではないか——そう信じて、筆を執っている。
一連の投稿は、ささやかな思考実験であると同時に、他者との共有を意図したアジェンダでもある。そして率直に言えば、誰かがこの断片的な構想を見つけ出し、歴史に刻んでくれることへのささやかな期待——「アリバイづくり」という下心も、全く無いとは言えない。
私は十数年前に、情報学部を中途半端な卒業制作で乗り切った程度の学士であり、論文に関する指導も回避したクチである。何らかのデータや詳細な引用、数値分析にも長けているとは言い難い。カール・マルクスらの『資本論』と同様に、数式もほぼ登場しないだろう。
現代社会や市場に適合しているとは言い難い暇人による屁理屈というか、自由な乱文・散文として、思考の過程を記していきたい。
言い訳が長くなったが、まだ本題には入らない。もう少しだけ、本題前の整理にお付き合いいただこう。
情報主義社会、もしくはポスト資本主義、ポスト産業社会について
私は1988年の早生まれであり、2000年に小学校を卒業し、2010年に四年制大学を卒業する教育課程を経てきた。中学・高校の世界史や公民といった教科では、ブルジョアに虐げられた労働者が蜂起し、資本主義から社会主義・共産主義へと至る「二段階革命論」や、ハーバート・スペンサーらの社会ダーウィニズムに影響を受けたマルクスの「唯物史観」を学んだ記憶がある。
また、社会というものが、物々交換や狩猟採集に基づく原始的な共産制を出発点とし、奴隷制・封建制を経て、やがて社会主義へ発展していくとする「社会進化論」。そして、「先進国=進んだ社会」「発展途上国=遅れた社会」といった捉え方があることも、それとなく学んでいる。
同時に、社会主義・共産主義を掲げた国々や国内の政党が、その後どういった顛末を迎えたのかという歴史的事実も、私たちは目にしている。
そうした前提に立って考えるなら——資本主義の次にある社会の姿として、既に「失敗」と見られている社会主義・共産主義に代わって、自然と浮かび上がってくるのが「情報主義」という考え方ではないか、というのが素朴な発想だろう。
ただし、ここで前提としてはっきり述べておきたいのは、私自身は「唯物史観」や「社会進化論」に対して否定的な立場を採っているという点だ。時代が進むにつれて、科学技術や知識は確かに発展してきたものの、個々の「人間」としての本質は、産業革命以前だろうと、紀元前だろうと、大きく変わらないと思っている。
たとえば、フェと呼ばれる石貨を担ぎながら信用取引を成立させているポリネシアの人々を、「未開」とか劣っているとは全く思わない。都市で求められる能力と、農村や田舎で求められる能力が違うのと同じように、歓迎されるパラメータが異なるだけに過ぎない。
現代のリベラルが敬遠される原点となったのが、「自然選択」という科学理論に対して、スペンサーらが「適者生存」という余計な思想を混入し、それをダーウィンが肯定してしまったことだと考えている。
あのタイミングで、「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である」といった社会進化論や優生学を、ダーウィン自身がきちんと否定してくれていれば、歴史は大きく違っていたのではないか——そんな空想すらしてしまう。
なお、「情報化社会」や「情報社会」ならすでに実現しているではないか、という指摘や「情報資本主義」として第三次産業が大きくなっているという見方もあるかもしれない。これらはあくまでも「資本主義」という枠組みの延長線上にあるものであり、私が扱おうとする「情報主義」とは、ニュアンスも性格もやや異なっている。
いずれにせよ、ポスト資本主義、あるいはポスト産業社会として、「情報主義社会」の構想を提示することは間違いがないので、その点はご安心いただきたい。
資本主義で見えてきた課題
マルクスは『資本論』を「商品の分析」からスタートし、商品の価値から労働の価値や交換性へと論理を展開した。しかしながら、この建て付けには様々な問題が隠れている。
例えば、商品の価値と価格はイコールではないし、商品の価格は需要と供給によって決まるため、生産に費やされた原価とは、直接的な関わりはない。間伐材を削って割り箸を作るのに、時給1,000円の労働者が1時間で一膳しか生産できなかったからといって、一膳1,000円の割り箸を購入するだろうか?
非常に手間暇がかかっていて材質も良い価値の高い割り箸だったとしても、市場で取引が成立する価格はもっと低いだろう。「割り箸はタダでもらうもの」という相手なら、取引自体成立し得ない。
唯一無二性や希少性が高い国宝や重要文化財といったものも存在するが、価値が非常に高くても「所有したい」とか「欲しい」といった声がなければ、価格は定まらない。市場流通性は低いため、公共財として実質的な価値は霧散するように思えることも多々ある。
また、国外との取引や金融商品の価値変動、為替といったものも考慮されていない。マルクスは、資本を「自己増殖する価値」と捉え、それが無限に拡大すると考えたが、実際には貨幣も金(gold)も価値は変動する。海外からの投資や資金の流出、あるいは生産設備や労働者の移動も自由を認めれば、価値も基準もダイナミックに動き続ける。
さらに、マルクスはあえて言及しなかったのかもしれないが、市場価値に関わらない「場外」という問題がある。典型例は行政やインフラ、テクノクラートとなってくるが、「商品の価値」を基準に算定したところで、元々噛み合うはずもない領域だ。それにも関わらず、市場の外にある存在に対しても、「商品の価値」を元にした「労働力商品化」、端的に言えば被雇用者の時間給や賃金を割り出している。
貨幣取引や信用取引が発達し、金本位制や兌換性といった物理的制約から切り離されたことで市場経済は自由化・民主化が加速した。その過程で、地縁や身分に縛られない「職業選択の自由」も広がり、「どこで何をしてもいい」という近代的な自由の確立にも、労働力の商品化や時間給の概念は一定の貢献を果たしたと言える。
農村部で後継者でもなく、特殊な技能も持たなかった知的エリートたちを、都市部で官僚や教育者、行政やインフラに関わる職能集団として組み入れ、「必須とは思えない書類仕事」や「社会的意義の乏しい会議・調整業務」――いわゆるブルシット・ジョブを割り振ることで、「時間が費やされている」という理由だけでそれを「労働」として正当化する構図が成立した。
本来なら「田舎に帰ってもらう」ほかなかった人材を都市部へ引き留め、「食わせるため」に余計な仕事や利権を創出する。ゴールドラッシュやアメリカンドリームが機能していた頃の米国や、一億総中流とされた高度経済成長期の日本であれば、見過ごされた方便だろう。しかし、現代では厳しい目が向けられているような気がする。
マルクスの『資本論』に存在する二つの重大な「穴」に、その原因があるようにも思える。一つは、行政機関や官僚といった「市場外の存在」を『資本論』の内部へ組み込まず、無視を決め込んだという点。もう一つは、「市場は閉じている」という勘違いを放置してしまった点である。
マルクスやエンゲルスの世界観はシンプルにモデル化された、予想しやすく安定した世界であって、外部から影響を受けることはない。そのため、『資本論』の世界には貨幣や金融商品の価値を左右するインフレやデフレ、証券取引や第三国との為替といった影響が考慮されていない。
同時に、「国際金融のトリレンマ」にも目配せできておらず、鎖国やブロック経済など特定の域内しか考慮しないモデルであれば、シンプルなモデルや考え方でも成立したかもしれないが、国際貿易や自由な資本移動が当たり前になれば、閉鎖系のモデルでは通用しない。
また、マルクスは「市場外の存在」を意図的に分析対象から除外することで、古くから支配層と結びついていた書士・書記官・官僚、そしてお抱え学者たちを、攻撃対象であるべきブルジョア階級から免責したとも言える。
しかもその構造は、マルクスからレーニン、さらにはロシアの知識人層へと受け継がれる過程で、「労働者を導くインテリゲンチャ」という特権的な存在の正当化する論理として取り込まれた。
その結果、生産手段や財産の共有ならびに平等を目指したはずの共産主義や社会主義は、「指導者」らによる寡頭政治や一党独裁、共産党体制に基づくイデオロギーが「法の下の平等」を骨抜きにする政治体制に着地してしまった。ナロードニキも、「人民の中へ(ヴ・ナロード)」を起源としながらも、「指導者とそれ以外」で一線を引く形で終わっている。
権力側に取り込まれたテクノクラートや、反体制的立場から出発したインテリゲンチャであっても、やがてメディアや出版、言論を通じて、アジテーションや世論誘導にも手を染めるようになった。
たとえば、アドルフ・ヒトラーの『我が闘争』や宣伝大臣ゲッベルス、民主主義国家アメリカにおけるリップマンの『世論』、バーネイズの『プロパガンダ』、さらには戦時下日本の花森安治など──こうした人物たちの足跡は、全体主義と知識人、そして既得権益との親和性の高さを如実に示している。
かつては科学技術や芸術に対して誠実だったはずのメディアや人文学系アカデミズムも、今日では既得権益におもねり、自らの特権や資金源が失われないよう、格差の固定に加担しているように見える。
彼らは「グローバリズム」と「市場外」という二つの構造的な“穴”を巧みに突き、潜在的に脅威となり得る民衆の労力を空費させ、押さえつけようとしているのではないか──そんな疑念すら抱かせる。
先進各国で広がっているように見える、人手不足と産業の空洞化。
行政主導で最低賃金を引き上げたとしても、資本家には対抗手段がいくつも存在する。より安価な労働力を求めて生産設備を国外へ移転すればよく、合法・非合法を問わず移民を招き入れるために、メディアやアカデミズムを通じて、官民の世論に働きかけても構わない。
規制緩和の繰り返しで対象範囲が拡大し続ける非正規雇用を利用する選択肢もあるし、アウトソーシングや業務委託という形も採用可能だろう。
今では、地方行政が派遣社員に支えられていても誰も驚かない。人手不足を背景に、都道府県庁の職員や公共交通の運転手として、日本語すらおぼつかない外国人に募集をかけることも、もはや珍しくない。
ただし、これでは賃金を引き上げる余地がない。行政や官僚の賃金がこの有様では、その鏡写しであろう市場内の賃金体系──とりわけ時間給の制度においても、資本主義の建前が破綻しているように思える。
そこへ更に「市場外」が乗っかってくる始末。
国際機関やNGO、社会起業家らやNPO、特定の団体など、「市場外」から市場では成り立たない分野を補完したり、フリーライドする程度なら可愛いものだが、それらは「脱炭素」や「DEI」、「動物愛護」といった耳障りの良いお題目を掲げつつ、時に市場参加者へ攻撃を仕掛けてくる。「場外乱闘」と呼ぶべき状況だ。
耳障りの良いお題目により、補助金や助成金を分配してもらい、政商らが政治家と結託して利権化させるため、多少の不正や不公平さは不問とされてしまう。日本国内でも、明らかに怪しい会計処理でも、税務署から目溢しをされ、住民訴訟で開示請求を求められても黒塗りの資料しか出されないようでは、真面目に働くインセンティブは働かないだろう。
大衆は「市場」のルールに則って経済活動に貢献したところで、資本家は吸い上げた資本を出し渋り、タックスヘイブンや寄付といった形で抜け道を探す。少しでも安価な労働力を求めて新天地を開拓したり、移民を求め続けた結果、良い商品を生み出したところで購入できる消費者は極一部となる。
日本に限れば、真面目に働いたところで、社会保険料も含めれば五公五民を超える按分で国庫に吸い上げられ、最低賃金や物価上昇に合わせた基礎控除の引き上げを求めても無碍にされ、コストプッシュインフレに対抗するための消費減税や、昨年末に三党幹事長で合意したはずの、暫定税率廃止の法案すら、国会でマトモに通らない。
真面目にコツコツ働くよりも、助成金や補助金を食い物にしたほうが効率が良く、金回りもいい。ルールに縛られる市場内よりも、ルールの外で既得権益に寄り添うほうが、よほど効率的で「賢い」生き方に見えてくる。
生産性向上やDXを口実に、規制緩和や投資を促しつつ、一方では新自由主義や緊縮財政のもと「小さな政府」を標榜する。しかしその実態は、「取って配る」型の大きな政府によって利権を構築し、格差を固定化させる方向へ注力しているように見える。
これでは、自由主義も資本主義もすでに破綻しており、全体主義化した隠れ共産主義とも言うべき異形の体制に変質しているのではないか。しかもそれが美名の元、巧妙に隠蔽されている分、かつての社会主義や共産主義よりも、はるかにグロテスクなものに思えてくる。
かつてヨハン・ホイジンガは『ホモ・ルーデンス』で「遊び」という虚構と、それを破綻させる「ルール破り」を論じた。ダロン・アセモグルらも、『国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源』において、不公平なヒエラルキー構造が国家を衰退させると指摘している。
現在の資本主義を再構築する鍵も、「公平」や「法の下の平等」にあるのではないだろうか。ドナルド・トランプ米大統領は、第二次政権において不法移民を締め出し、自国の労働者と雇用を守ろうとする姿勢を示している。欧米各国も、生産手段を含めた「自国優先」の右旋回を強めている。
これらの動きは、行き過ぎたリベラルの反動というよりも、壊れかけている資本主義を立て直し、民衆に「働くインセンティブ」や「公平性」を取り戻すための試みなのではないか。
貨幣経済の発達と、金本位制や兌換性の廃止によって、経済はより自由に、民主的なものへと変化してきた。さらに情報発信や編集・編纂の技術までもが民主化されることにより、かつてはテクノクラートが握っていた優位性や特権は、生成AIの登場と相まって、日々縮小しているように思える。
被雇用者の「時間」や「労働の価値」を起点とした社会体制、そして知識や情報発信を障壁として成り立っていた擬似的な権威主義や特権構造は、もはや維持不可能だろう。
長らく支配的であり続けたマルクスの絵空事も、いよいよ終焉を迎えつつあるのではないか。これが、本題へ入る前提として共有しておきたい、基本的な立ち位置である。