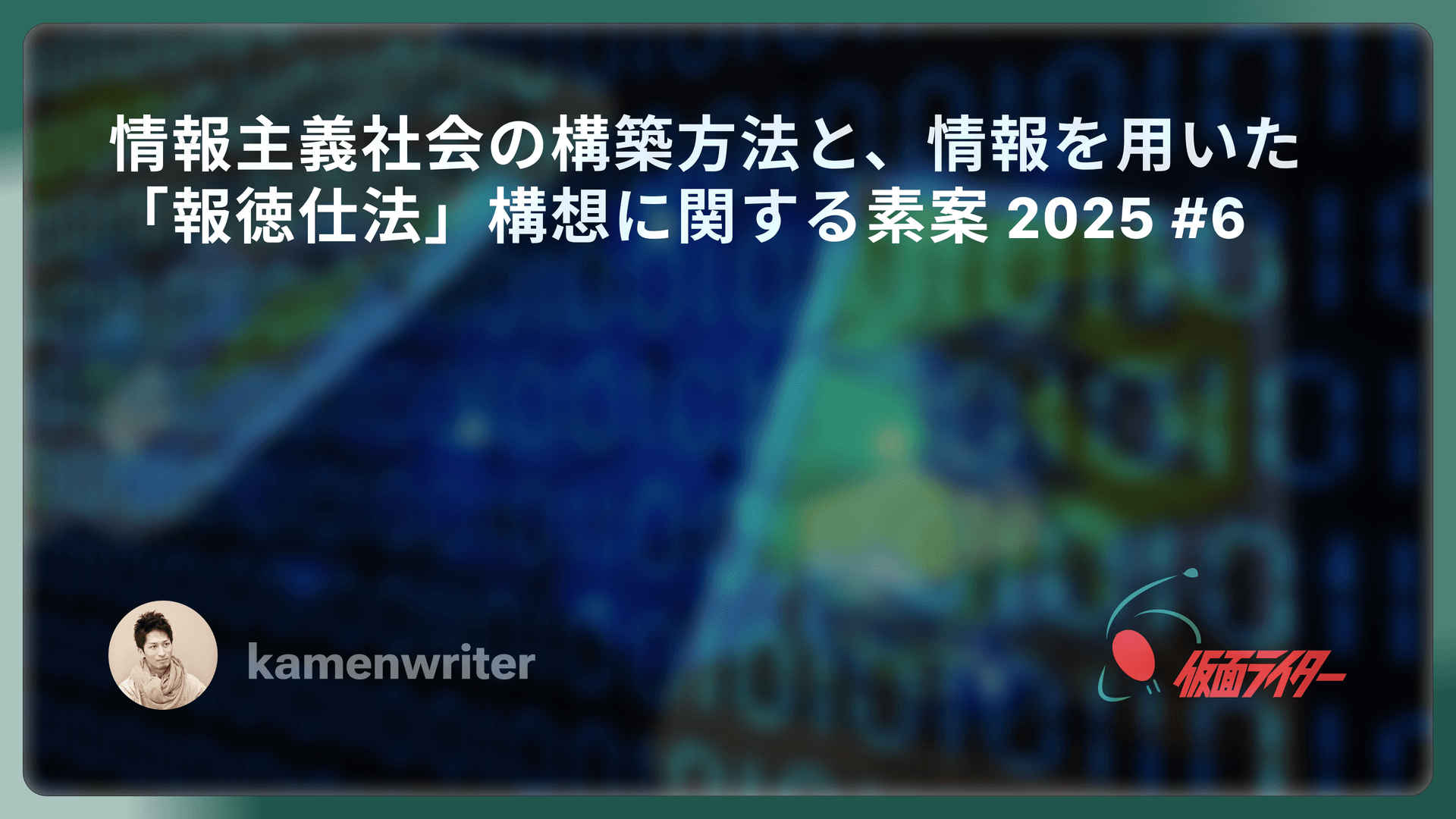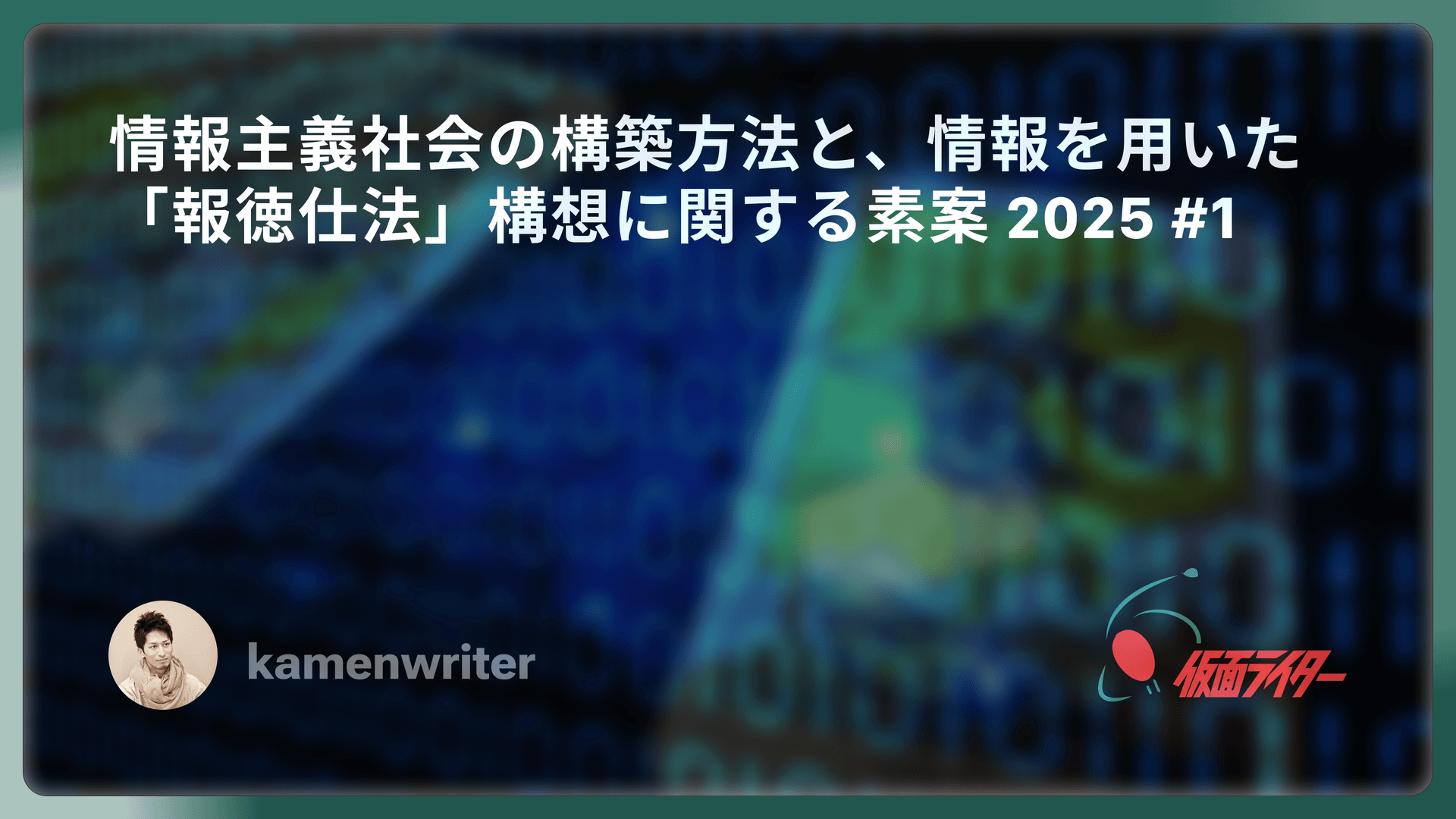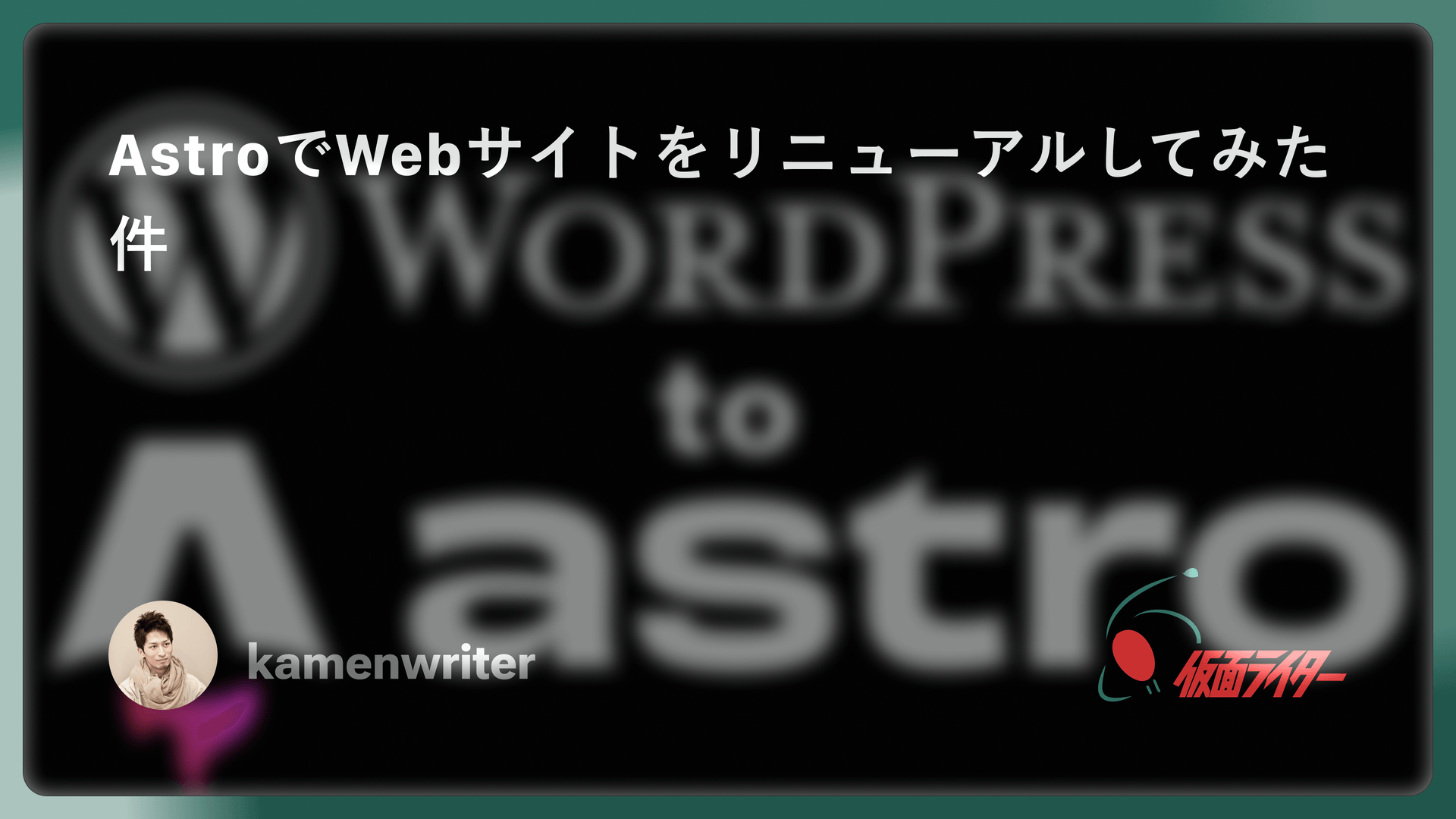第二章 情報の価値と未来予測
第一節 情報の価値基準
情報をそのまま通貨や流通財として扱うためには、価値の尺度や基準が課題となってくる。
情報資本主義の文脈であれば、自他が有する情報の非対称性や、OSINT(Open Source Intelligence)やSIGINT(Signals Intelligence)、HUMINT(Human Intelligence)を通じて入手した「インテリジェンス」から得られる競争優位性、コンテンツ産業やメディア事業としての商業的な価値や、宣伝・販売促進の効果効能といった物差しを使えるが、資本主義の文脈へ下ろさず、情報主義の領域内で完結させる場合、そうした「基準」をそのまま適用することは難しい。
また、新たな概念だからといって、全くのゼロから基準を作り上げることも現実的とは言い難い。
無用な「車輪の再発明」を回避するためにも、情報産業の世界で先端領域を走る二人の巨人、GoogleやOpenAIらの尺度を一つの参考としよう。
コンテンツやドメインに対するGoogleの評価アルゴリズムは、検索エンジン向けの最適化(SEO)という目的に特化しており、その内部は基本的にブラックボックスである。しかし、Googleが公式に公開している「SEOスターターガイド」や検索品質評価ガイドラインは、少なくとも「良質な情報」や「信頼にたるドキュメント」とは何かを考える上で、有力な補助線となり得る。
さらに、OpenAIをはじめとする大規模言語モデル(LLM)開発事業者にとっても、学習に有益とされる情報の多くは、Googleが重視する尺度と大きく矛盾しない。つまり、GoogleとOpenAIがそれぞれ異なる目的で築いてきた評価基準は一定の整合性を持っており、「情報の価値」に対して有力な基盤となる。
Googleの評価アルゴリズムは、大別すると「ドメインへの評価」と「コンテンツそのものへの評価」のに系統に分かれる。
前者はいわゆる「サイトパワー」や「ドメインエイジ(運用歴)」、「ページランク(≒被リンクの質や量)」などが該当し、コンテンツが掲載されるサイト全体に対する信頼性や評価のベースとなる。
後者は、個別のページや記事、あるいは書き手に対する評価であり、「E-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)」を中核とする「検索品質評価ガイドライン」に基づいて判断される。
ここに「コピーコンテンツでないこと」、唯一性や独自性、速報性といった要素が加点対象となり、近年では表示速度やモバイル対応、ユーザビリティなどの「ページ エクスペリエンス」も評価に組み込まれている。
この中で、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)といった、市場性や社会的文脈に強く依存する要素については、「情報」単体ではどうにもならない部分が大きいが、Experience(経験)や独自性に関しては、「情報」単体でも価値を左右し得るポイントとなっている。
なお、SEOにおける「ビッグキーワード」的な競争や、それに付随する資本主義的な背景を一旦括弧に括り、自分自身の専門領域や個人的な文脈にフォーカスしてしまえば、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)といった要素も、「情報」を保有する個人の裁量へ収納できる。
いわば「No.1商法」にも似た構造ではあるが、資本主義や市場経済の重力圏から意図的に離脱しようとする「情報主義」の立場からすれば、それもまた有用な振る舞い方である。
余談が長くなってしまったが、情報の価値基準としては、(個人にフォーカスした)E-E-A-Tと、唯一性や独自性、新規性(もしくは新奇性)が主要な候補として浮かび上がってくる。
第二節 情報の連なりとブロックチェーン
情報の価値を考える上で、唯一性や独自性、新規性(もしくは新奇性)が重要な指標であることは前節で述べた。しかし、価値の源泉を「一点」として捉えてしまうと、それ自体が過剰な差別化競争や先鋭化を招き、結果として資本主義的な過当競争の再演に繋がりかねない。
「情報」をストーリーやシナリオと区別することにした理由も、ここに通じている。コンテンツの価値を「誰もやっていない特別なもの」として過剰に評価してしまえば、寡占と排他性を招き、流通財としての普遍性を損なってしまう。
だからこそ、本稿で定義する「情報」としては、個人の経験や感想、新たな発見といった素朴なものも含めて包摂し、誰もが生産可能な多孔性、流通財としての普遍性を保つことを重視したい。
そのためにも、「点」としての価値だけではなく、それらの情報がどのように連なり、どのような文脈や系統図を形作っているのか形成しているか──つまり「連なり方」──を、価値を検討する上での要素に組み入れるべきである。
こうした情報の連鎖性や関係性、いわば数珠繋ぎの様子を理解する補助線隣、記録性や信頼性の担保を可能にする技術こそが、まさにブロックチェーンである。その実態や堅牢性については次節に譲るとして、本節ではまず、この「数珠繋ぎ」そのものに注目したい。
例えば、数珠を構成する珠の数や色が同じだったとしても、その並び方によって、受ける印象は全く異なるだろう。これは、0と1の組み合わせによって無数のパターンが生まれる二進数のようなものでもある。桁が増えるほどに、組み合わせと表現のバリエーションは爆発的に増加していく。
この性質は、経験や感想、発見や閃きといった「情報」においても同様である。
例えば、毎朝トーストとコーヒーという習慣を続けている人が、週末だけフレンチトーストやパンケーキに切り替えるのと、日によって米と納豆、シリアルと牛乳などをランダムに選んでいる人が、ある日同じようにパンケーキを作るのとでは、同じレシピであっても手つきや感想には、違いが生まれるだろう。
あるいは同じ家に暮らし、朝食と夕食を共にしている夫婦や兄弟でも、昼食が異なれば、その日の夕食に抱く感想も、また異なるかもしれない。遺伝子的にはほぼ同一である一卵性双生児ですら、それぞれが違う瞬間に違うことを経験し、その積み重ねとしての「連なり」は時間が経つほどに自然と差異を拡大していく。
同じ出来事を経験し、同じ情報に触れたとしても、それまでに何を見てきたか、どう感じてきたかによって、その後の気づきや行動には違いが現れる。この「連なり方」の違いそのものが「個性」と呼ばれたり、「その人らしさ」の源泉となるのではないだろうか。
そして、その差異や重層的な価値を正確に捉え、記録し、保証するヒントが、ブロックチェーンのような技術にあるのかもしれない。
肉体的な多様性や差異を拡大する仕組みが有性生殖であり、その記録媒体が遺伝子であるのなら、精神的・思想的な多様性や差異、エピジェネティックな履歴を担うのもまた、ブロックチェーンのような構造ではないだろうか。
私はつい先日、ユニークさや経験、そして遊びについて、「経験を情報の連なり=ブロックチェーン」として捉えた見解を述べている。
個人の経験や閃きといった素朴なものも、「情報」や流通財と認めることにより、ほんの一分一秒でも、あるいは一日を生きた痕跡や、何かに取り組んだという事実が、1円や10円相当の極めて小さな価値であっても、通貨になり得るようにしておきたい。
特別な成果や頑張りが加点として評価される一方で、それらがなかったとしても認められる世の中──生きているだけで価値があると思える社会であって欲しいという、素朴な願望も込めて。
第三節 CBDCあるいはセキュアなポイント制度構想
「情報」の価値基準や、「情報の連なり方(=擬似的なブロックチェーン)」までを価値として拡張することはできたとしても、実際にそれを流通財、あるいは通貨として機能させるには、もう一段の飛躍と、それを支える制度的・技術的な補助線が必要となる。
そこで大きなヒントとなり得るのが、CBDC(中央銀行デジタル通貨)である。
CBDCとは、各国の中央銀行が発行するデジタル形式の法定通貨であり、ブロックチェーンをはじめとする分散台帳技術や、量子コンピュータ時代に対応した暗号技術の活用が前提とされている。法定通貨としての安定性と同時に、個人単位でのトランザクションを精密に管理・記録する仕組みが組み込まれている点が特徴的である。
本稿で構想している「情報」を流通財と見立て、法定通貨のように換金せずにそのまま流通させるとすれば、必要になるのは、情報の「連なり」──すなわちその発生と伝播の履歴──を正確かつ不可逆的に記録・蓄積できる技術である。
ここで、分かりやすくするために「擬似的なブロックチェーン」をエピジェネティックチェーンと呼称して、より具体的に考えてみよう。
例えば、第三者が保有する「情報」に触れることで、新たな感想や経験が生まれ、それが自らのエピジェネティックチェーンに記録される。また、自ら新たな「情報」を生み出し、それが誰かのエピジェネティックチェーンを変化させる──そうした連鎖が、単方向あるいは双方向に作用しながら、情報が自己再生産的に増殖していく構造を想定している。
このように、「情報」が流通し、記録され、影響し合いながら蓄積していくプロセスを制度的に支えるためには、CBDC的な設計思想──セキュアな暗号化、分散記録、検証可能な履歴保持──が大きなヒントとなるのではないか。
「情報」を換金せず、そのまま流通させたとしても、結局のところ、その量的変化や可動性については、何らかの履歴管理や記録保持が不可欠となる。これを保証するには、間接的なトークンとしてのCBDC、あるいはそれに準ずるセキュアなポイント制度のような枠組みを別途設計する必要がある。
こうした基盤なしには、「情報主義」を支える秩序は成立し得ず、またその秩序に参入しようとする人々へのインセンティブも適切に機能しないだろう。
この点こそが、「情報主義」の実現における最大にして最難関の課題である。
第一の関門は、CBDCそのものが中央銀行によって発行される「法定通貨」であるという点だ。いかにデジタルとはいえ、これを民間が正面から模倣し流通させることは、制度的にも倫理的にも不可能に近い。反社会的な地下経済で生き延びることはできても、善良な市民として社会に留まりたいのであれば、CBDC的なシステムを堂々と実装しようと考えること自体が危ういだろう。
第二の関門は、CBDC並みのセキュリティや暗号技術、分散記録システムの実装にかかる技術的・財政的な負荷である。仮に技術的な見通しがあったとしても、運用責任の所在や補償リスク、法的な整備などの面で、国家レベルの支援と関与がなければ成立し得ない。個人や民間の一団体が手を出すには、あまりにも荷が重い。
第三の関門は、規模の拡大と信用の問題だ。仮に交通系ICカードや地域通貨のような制度を構築できたとしても、実際にどれだけの人や企業が参加し、使い続けてくれるかは全くの未知数である。メリットも曖昧、法的位置づけも不明で信用も保証もないとなれば、人は動いてくれないだろう。
ゲーム内通貨のように閉じたエコシステムでの報酬設計や、セカンドライフのリンデンドルのような仮想経済における事例もあるが、これらも法的にはグレーゾーンに近く、現実の通貨や公共制度の代替にはなり得ない。
資本の流通を介さず、「情報」という別の文脈でやり取りを成立させることができれば、資本主義の元で不可避となっている負担増などを回避しながら、それでも経済を活性化させるインセンティブは働くのではないか──そんな淡い期待もある。
とはいえ、現実的には「情報」だけで完全に自立し、自走する経済圏の構築は難しく、結局は資本主義や既存市場との接続口を設け、その中に取り込まれていくという帰結を免れない。
地域通貨に近いポイント制度などでワンクッション挟むことができれば、理想と現実の緩衝地帯を作れるかもしれないが、最終的には貨幣経済へ帰らざるを得ない。誰がその変換コストを担い、どの地点でその負担を解消するのか──この問いは常に付きまとう。
鶏が先か、卵が先か。
情報主義として一歩を踏み出そうとする時、この「資本主義との接続の設計」こそが、最大のボトルネックであり、進みたくても進めないもどかしさの正体となっている。
「情報主義」として自立・閉域的に完結できないという構造的な弱点に加え、情報を流通財と見なした際に必要となる複式簿記に相当する記録体系や、債券・株式といった信用取引の仕組み、銀行や証券会社といった制度概念の整備については、思考が及んでいない。
本稿で述べてきた「情報の価値化」は、こうした現実的なハードルを抱えながらも、未来像を探るための一つの思考実験である。
私にできる範囲で考えを整理し、好き勝手に放言しておけば、いつか誰かがこの構想を引き継ぎ、発展させてくれるかもしれない。
未解決の課題があるという前提のもと、ここから更に議論を進めてみたい。