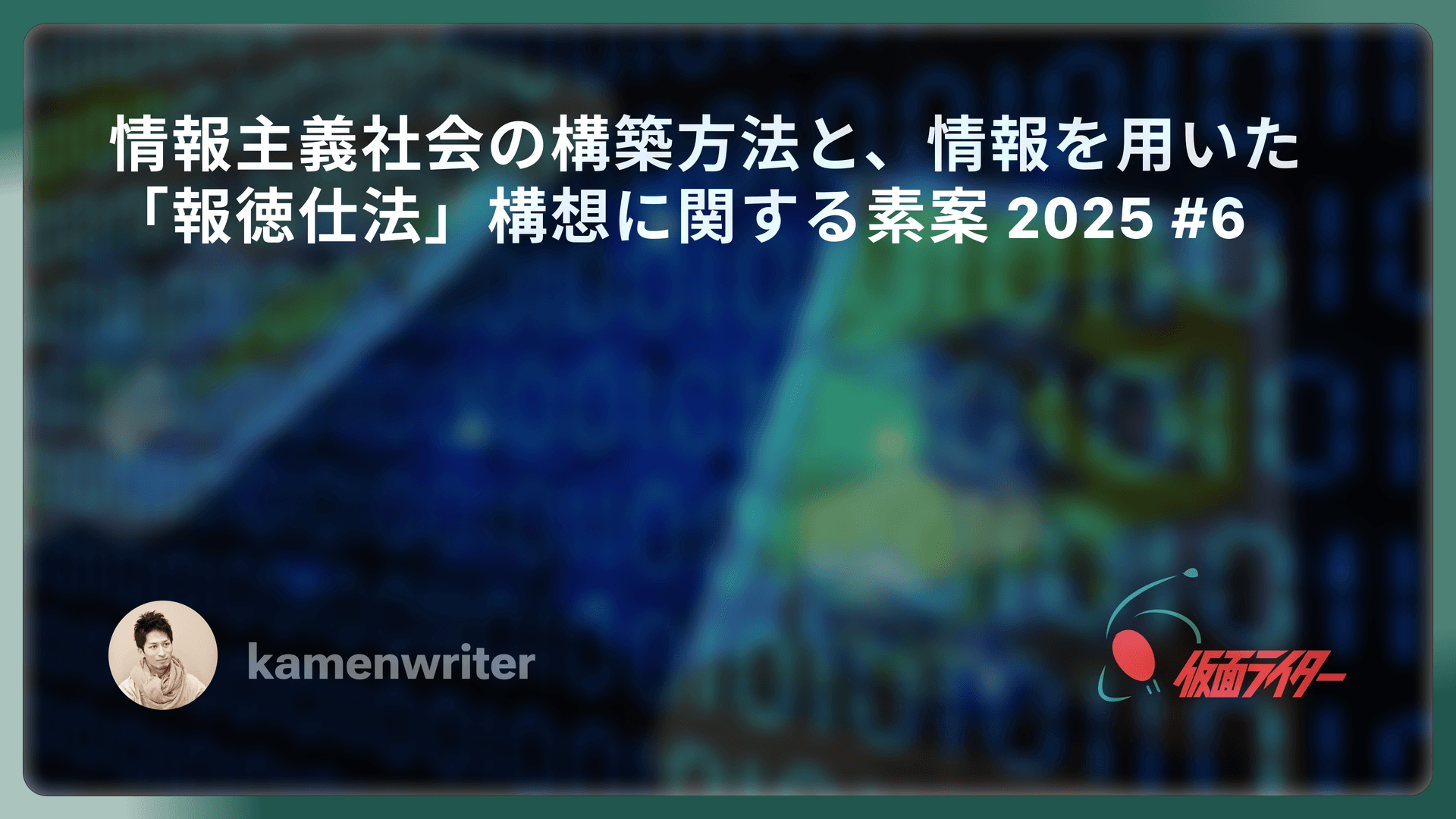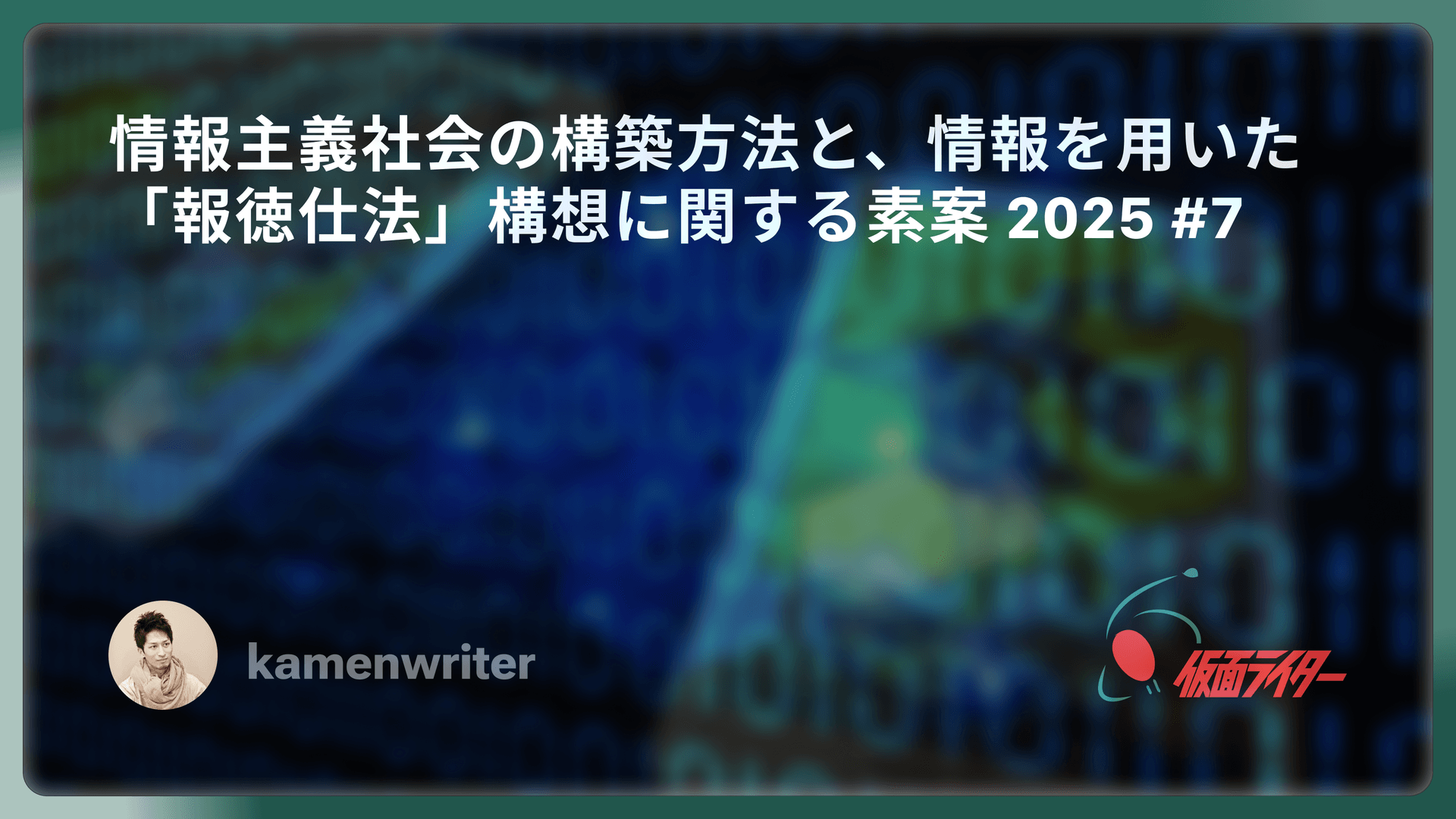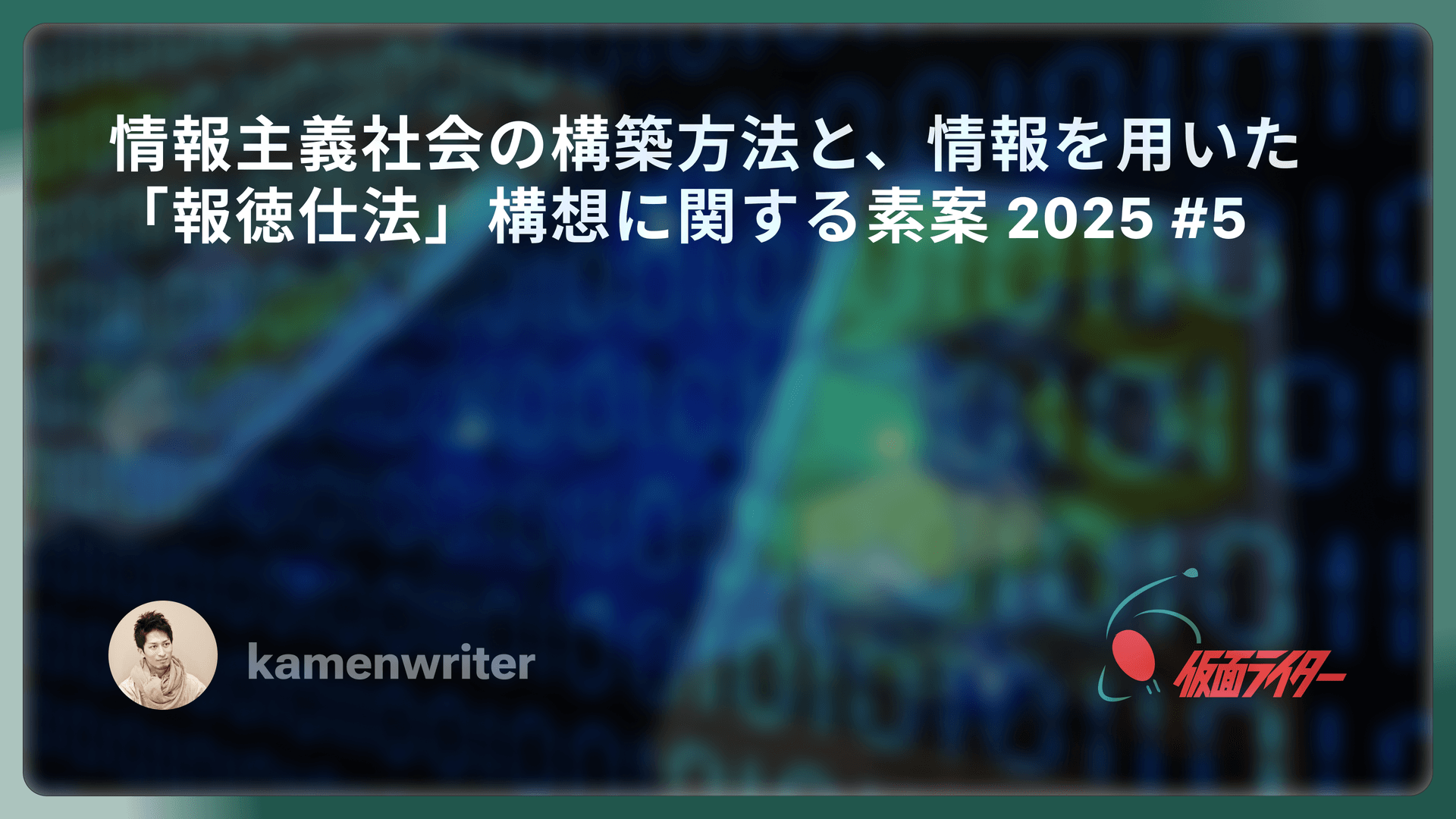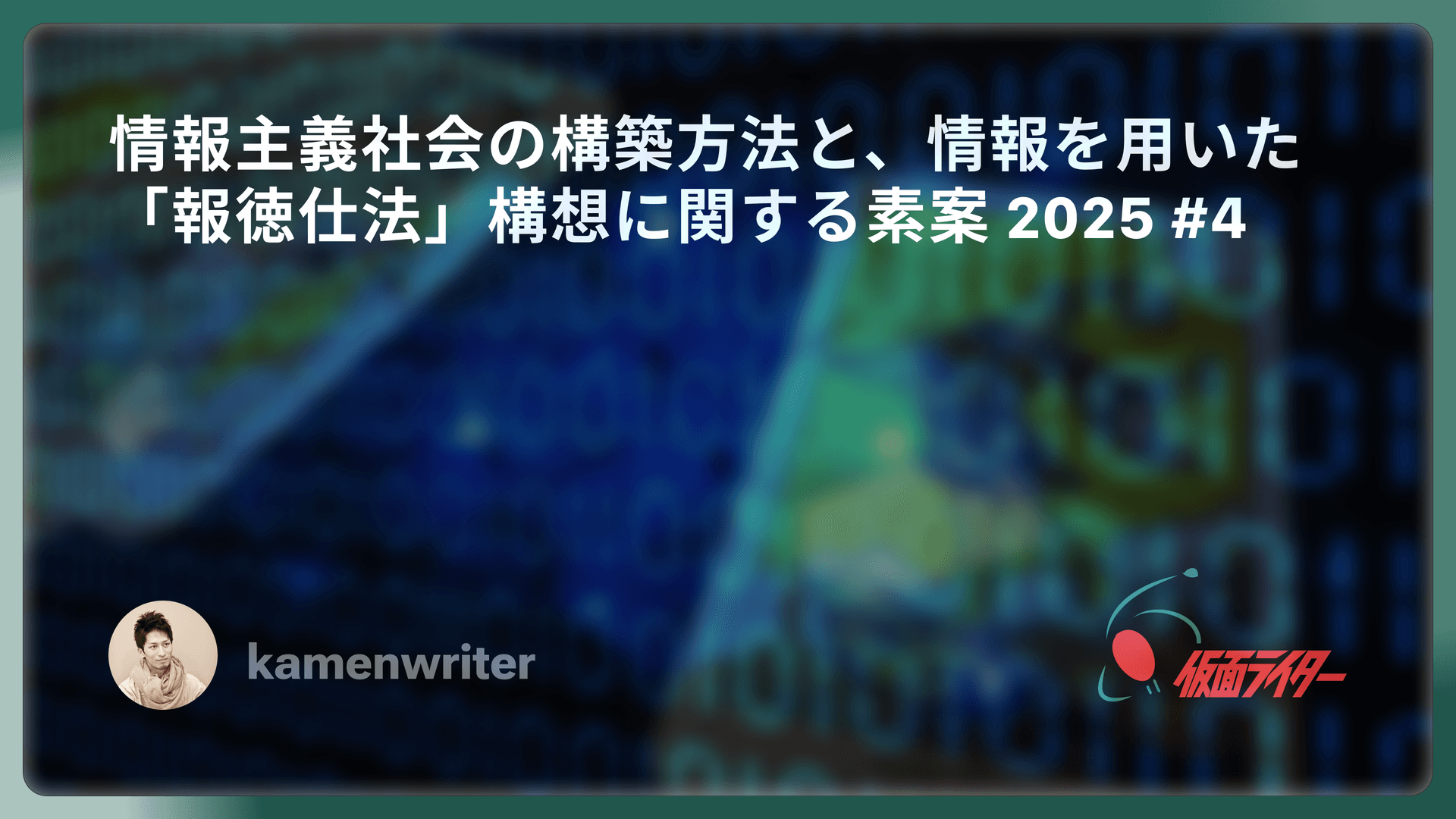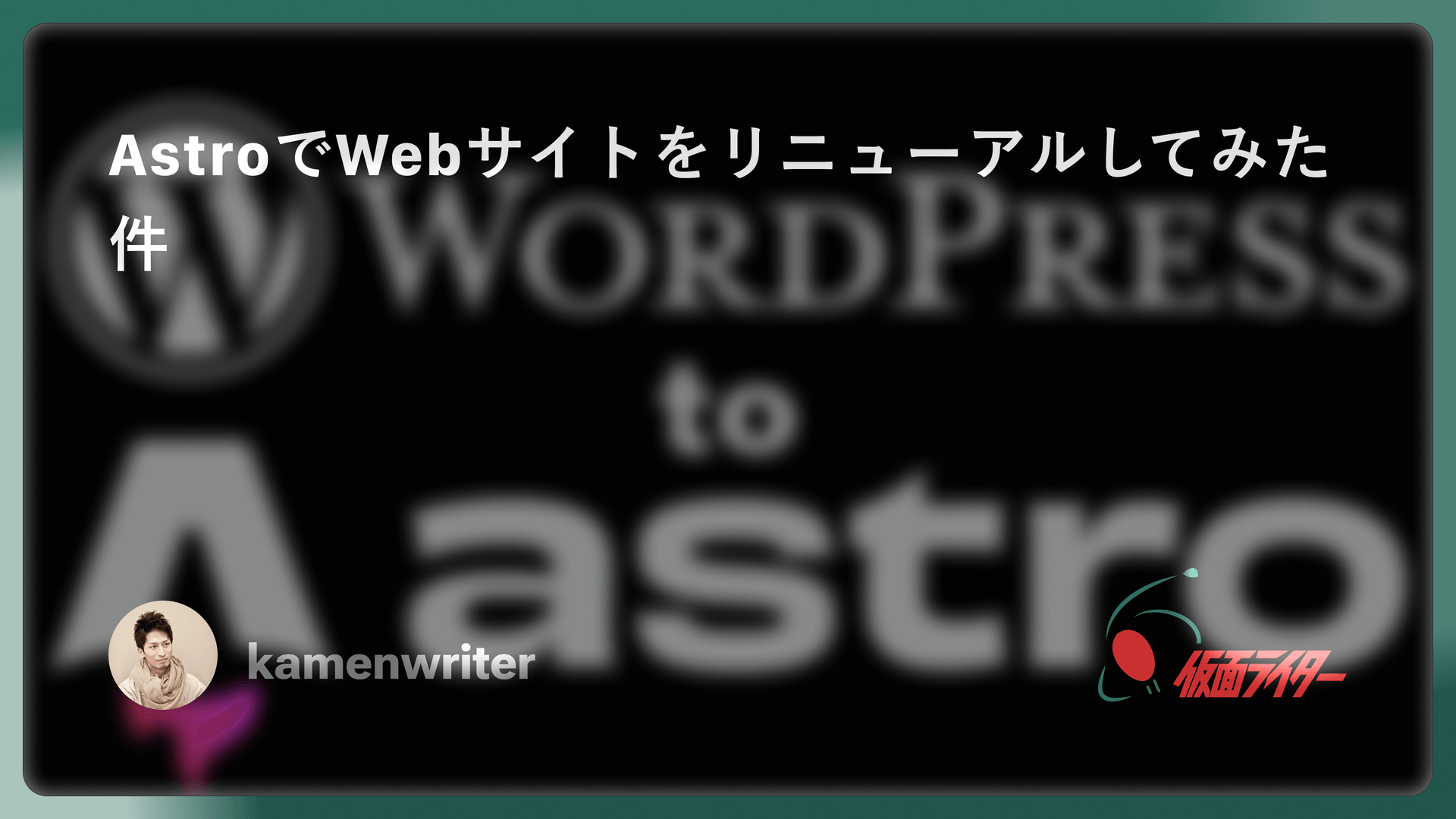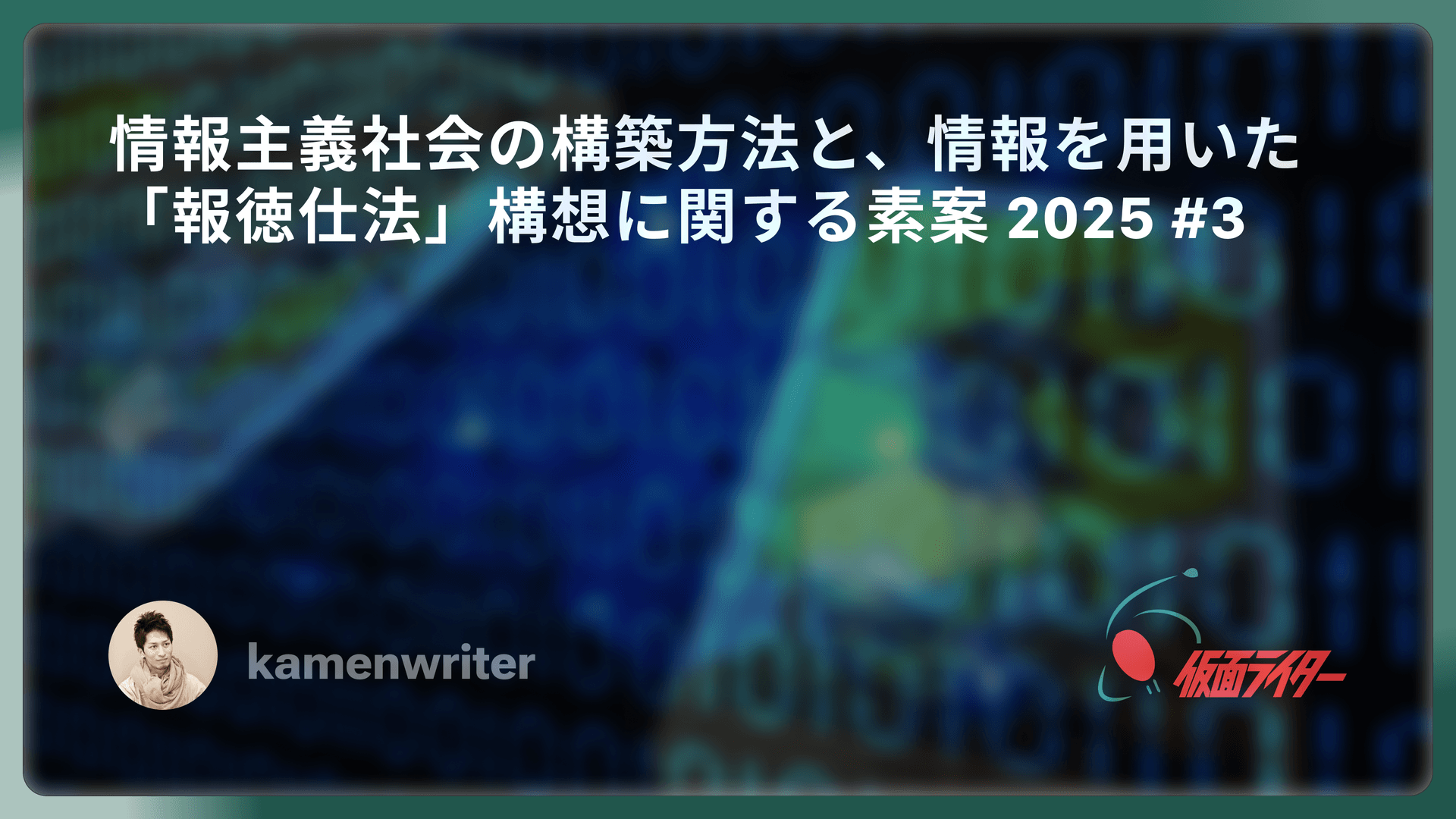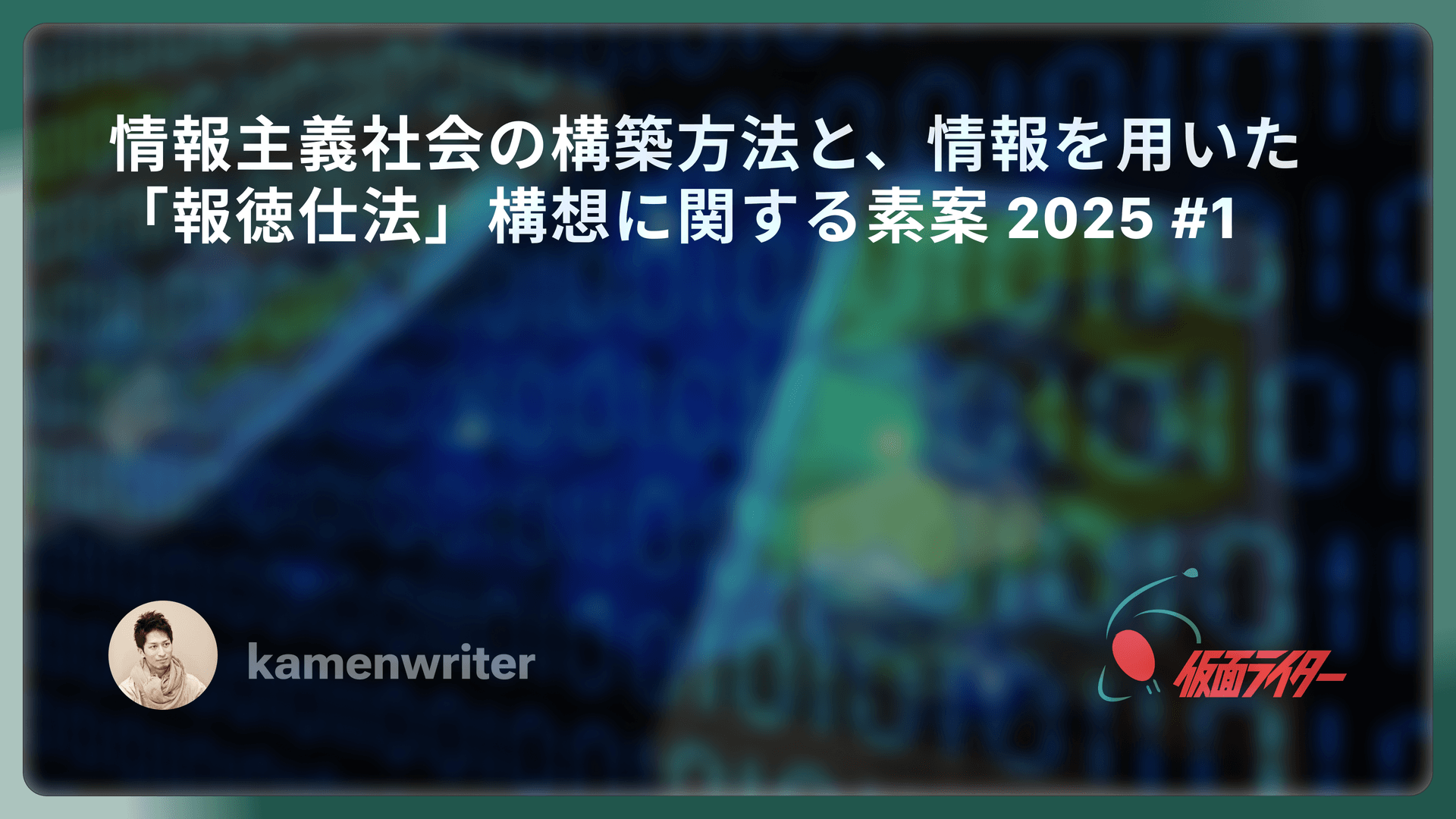第四章 素材もしくはツールと課題
第一節 Web制作者としての素材もしくはツール
第三章の終わりでは、「思考が及んでいない」や「ここが限界だ」と、ある種の行き詰まり感を率直に示したが、それで筆を置いて仕舞えば、尻すぼみで終わるだけになってしまう。
建設的な議論として成立するかは分からないが、現在の手元や足元にある素材やツール、個人的な課題についても記しておくことで、手探りながらも前へ進む手がかりとして役に立つかもしれない。
Webサイト制作やマーケティングに携わる実務者として、すでに準備できていることや、現時点で提供可能なものを、まず整理しておこう。
第一に挙げられるのは、「制作」や「所有」そのものではなく、「使用」や「公開後の運用」に重点を置いたWebサイト制作である。WordPressを用いたものについては、BLUE B NOSE(略称:BBN)として展開しており、Astro.jsを用いたJamstackベースの静的サイト(SSG)も提供可能である。
発注者の承認欲求を満たす「見栄えの良いサイト」を高額で請け負い、納品するのではなく、ユーザーが本当に求めている情報や、実際にビジネスとして役立つものを、できるだけ大きく間違えずに提供することが目的である。高速表示と豊かな表現を両立させながら、アクセスデータを基にOODAやPDCAを回して改善を繰り返す。アウトプットを手伝うことで思考を反芻してもらうことで、内面に秘めた衝動を絶対的なUSPとして掘り起こす、というのも狙いではある。
一回限りで「大きな数字」を追いかける「ハレ」の発想ではなく、エンドユーザーとの長期的な関係性や、ブランドとしてのエイジング、クライアントにとってはパターンオーダーからビスポークへの移行といった、地味で消極的な「ケ」を重視している。「いかに成功するか」ではなく、「いかに失敗しないか」。再現性の高い方法を選ぶスタイルを基調としている。
この段階で、クライアントが保有する「情報」や「物語」を整理し、必要に応じてフレーバーテキストの作成やWebプロデュース、ブランディング提案といった形で「情報の貸し付け」や「物語の貸し付け」に相当する支援も行っている。多少なりとも「情報」の価値向上には貢献できているはずだ。
また、クライアントに更新権限や発信手段を提供するかどうかにも左右されるが、コンテンツ制作や情報発信を代行・支援するといった、いわゆるコンテンツマーケティング的なサポートも提供可能である。
まだ本格稼働には至っていないが、UGCやリピート施策に特化した独自のアンケートもすでに実装している。ユーザーの声をそのまま拾い上げる構造になっており、本格的なユーザーインタビューを実施せずとも、「情報」の再生産や循環が期待できる。
さらに、クライアントが第三者に場を提供するようなビジネスモデルを採用している場合には、そのユーザーに対してもポートフォリオや個人サイトの制作を支援し、アンケートによる「情報」の循環をも促すことができるだろう。
クライアントからサブドメインをお借りし、そこに特別な下宿やトキワ荘のような形で、サブディレクトリ型の個人サイト、ポートフォリオをぶら下げていく。駆け出しのクリエイターや講師など、SNSだけでは不十分な「情報」を補強したい個人にとって、これは有効な足場となるだろう。
やがて本人が「独自ドメインを持ちたい」となったタイミングで自立してもらい、その際に初めて費用が発生するような「出世払い」の形にしておけば、クライアント側もパートナーとして、半ば強引に「情報の増加」に巻き込むことができる。
「情報」や「物語」を立ち上げ、時に貸し付け、時に循環するように背中を押す。経済的にもWin-Winの関係になることが予想されるため、そこまで悪い手法ではないと考えている。
作って公開するだけではアクセスが細く、SNSの活用にも課題がありそうなクライアントのWebサイトに対しては、発信力を補う方法として、BBN名義でRSSを集約するアンテナサイトやポータルサイトを構築したり、BBN公式アカウントから発信をサポートするという手段も考えられる。
BBN自体も、現時点でそこまでアクセスの多いサイトではないし、十分に育ったSNSアカウントでもない。しかし、ポータルやアンテナがある程度の流入を得られれば、そこに繋がっている各サイトにも間接的に還元され、結果としてWin-Winの関係性が生まれるかもしれない。
効果は限定的で過信はできないだろうが、完全な無駄とも言い切れない。
「SEOは死んだ」や「SEOではもう食っていけない」といった声を耳にするたび、「それならWebサイトなんて必要ないのでは?」と思われそうだが、そうとは限らない。
確かに、検索上位の獲得を競うようなSEOは飽和しつつあるところに、生成AIやSGEが当時した結果、大量のアクセスを前提とする施策やサービスは成立困難なものの、「一次情報」としての検索需要や、指名検索に応えられるかどうか――まともな公式Webサイトを持っているかどうかは、今もビジネス上の信用問題に直結する。
SNSがいつ方針を変え、いつ仕様やアルゴリズムを変えるか読めない状況下で、自前のWebサイトを持っておくことは、情報主義云々に関係なく、ますます重要となるだろう。
第二節 一クリエイターあるいは個人としての課題
ここからは、一人のクリエイター、あるいは個人の物書きとして手元にある「まだ形になりきっていないもの」や、より個人的な課題について語ってみたい。
まず挙げられるのは、CC0ライセンスで運用予定の、創作向けオープンデータ――オープンソースなシェアードワールドの準備と公開だろう。
例えば『小説家になろう』などで見られる「ナーロッパ(=なろう + ヨーロッパ)」のように、創作で完全オリジナルの世界観を一から想像することは骨が折れる。だからこそ、何かしらのベースやアセットがあるのなら使いたい、と考える創作者は少なくない。
そこで、ラヴクラフトを見習って(?)、作品を通じて自由に書き込み合うことを前提としたシェアードワールドの素材を整理し始めている。GitHubでの管理や、NoSQL・RDBへの流し込みも視野に入れつつ、現在はGoogleスプレッドシートを用いて、キャラクターデータ等を調整中である。
紙ベースのメモなど、未整理のアナログ素材が残っているため作業は停滞しているが、きちんと時間を確保して、なんとか後悔まで漕ぎ着けたい。
また、このデータには、各キャラクターを演じてもらう架空の俳優という形で、「ペルソナ」も設定してある。これらのペルソナは作品への出演歴を重ねるごとに、データの厚みや印象が増していき、架空の人物なりに魅力が培われる、スターシステムのような展開も考えている。
この「ペルソナ」を、そのままマーケティング用途へ転用することで、ペルソナマーケティングの精度向上やコスト削減にも貢献するのでは、という希望的観測も含んでいる。
ペルソナ自体に魅力や憧れの要素を持たせることができれば、それを活かしたプロモーションやブランディングも展開できるだろう。
例えば、売り出したい商品を作品中に登場させ、「私もああなりたい」という願望を刺激する。あるいは、ペルソナに実在のモニターのように商品を試させるシーンを、ショートストーリーとして発信することで、擬似的な使用感やライフスタイルを提示する――といったアプローチが考えられる。
消費者に対して、具体的な想像を膨らませるヒントや材料を提供できるという点で、「物語の貸し付け」に近い効果が期待でき、物語の規模によっては拡大再生産、循環もあり得るだろう。
また、既存の発信枠に対して、第三者コンテンツをAPIで配信するという構想も検討している。
新聞の四コマ漫画や連載小説、雑誌の占いコンテンツのように、掲載元とは直接関係なさそうでありながら、読者にとっては一番の楽しみになったり、継続利用のきっかけにもなる――そんな「埋め草」的コンテンツを、Web上でも再現できないだろうかという素朴な発想から始まっている。
オウンドメディアやSNSアカウントをいくら増やしても、発信するコンテンツが不足していたり、更新が停滞してしまえば意味がない。本体と無関係な第三者コンテンツの掲載がどのように受け止められるかは未知数だが、配信元がオリジナルであるというcanonicalを明示しながら、更新頻度を保つことにつながるのならば、一定のアクセスやリーチ強化には効果があるかもしれない。
作品を配信する先が増えれば増えるほど、配信元の発信力やコンテンツの価値、ブランド力も上がっていく可能性があり、参画してくれる作り手にとっても露出の機会が増えるだろう。潜在的なメリットやポテンシャルはそれなりにある仕組みかもしれない。
さらに、往年の文豪や文壇といった言論空間形成の歴史を踏まえるならば、リトルマガジンの方の同人誌やその延長としての出版、新たなメディアという展開も、頭の片隅に置いておきたい。 物理的な媒体の印刷や流通に伴う費用、そこに費やされる広告費といった資金の流れは、現代でも通用する一つの力となっているし、新潮社に全く恨みはないし、むしろ同社の文庫に書き手として仲間に入り、背表紙に色が着く所、選べる所へ至りたいとも思っているが、「ニューストリーム」を関する同社が130年近い歴史を持つというのは、その後の競争や展開はどうだったのか、無用な疑いを持ってしまう。
物理的な媒体や世代を跨いだ社会人サークル的な参加型を目指してはいるものの、結果的に個人の中途半端なメディアとして動かしきれていないNXZについても、当初の目的を果たせるように軌道修正や運用再開に注力したい。
もし、うまく動かせるのであれば、やがてはYoutubeのような動画やゲームのようなその他のメディア、コンテンツにも手を拡げていければと想像してみるものの、まずは目の前の一つひとつをきちんと形にして行かなくては。その積み重ねからしか、何も進まないのだからと自分に言い聞かせている。
最後に、社会人としても、物書きや表現者としても、何者にもなりきれていない私個人への課題として、「物書き」として「表現者」として、何者かになるという課題が残っている。
「情報」や「物語」の持つ力がどうのこうのと言い始めたところで、提唱者自身が中途半端なままでは、何の説得力もない。
今の私では、物書きとしても表現者としても、半人前どころか、それ未満に見られているのではないか――そう思えてならない。まずは書く力を筆頭に表現力を高め、世間的な評価を獲得することを目指す。そのために避けては通れない「作品作り」にも、真正面から向き合いたい。
短歌や俳句にとっての「季語」が、脚本における「柱」や画面構成にも通じると気づいたとき、自分に不足しているのは、シナリオ術と王道ベストセラーに向き合う覚悟なのだと再認識した。その辺りを改めてインプットしつつ、並行して取り組んでいる創作用オープンデータにも、作品作りの結果も反映できるよう、環境を整えていくつもりだ。
その上で、柳田國男の『日本の昔話』を種本とした、fakeloreプロジェクトにも挑戦したい。
同書に収録されている民話を分析し、ジャンルや形式を変えながら複数の掌編へリビルドし、文章修行と評価獲得を両立する動きにしていきたい。
それに合わせて、書きかけの中長編についても、最後まで書き切れるように改めて段取りを整えたい。
さらに、映像的な表現にも手を出す準備として、サウンドロゴや短い映像の制作といった、Youtubeチャンネルの整備にも、適宜手をつけていく予定だ。
非常に個人的な課題であり、ある種の所信表明にもなってしまうが――
今まで棚上げにしていた「やりたかったこと」、「目指したかったもの」へ向けて、ようやく全力で動き出そうとしている。それも、今の素直な気持ちである。